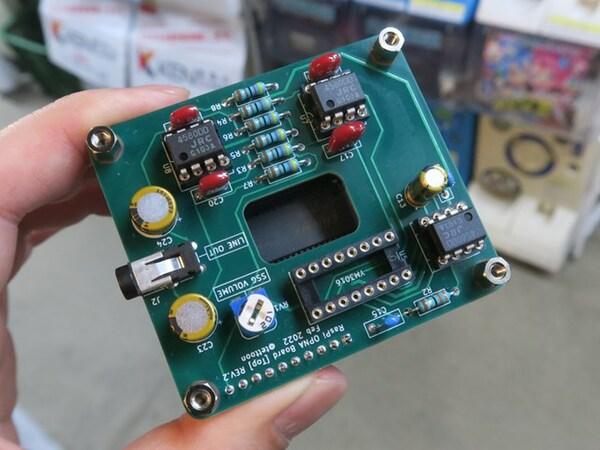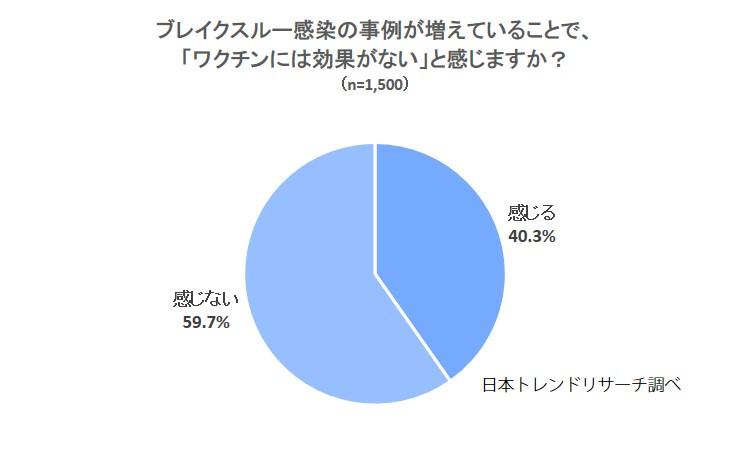世の中に存在するアルバムの多くは極めて短命なもので、人々を踊らせたり、笑顔にしたり、泣かせたりする曲の集合体だが、時として人は、1枚の特別なアルバムと強い絆で結ばれることがある。つまり、それを作ったミュージシャンやバンドの野望と構想によって成し遂げられた偉業に心を動かされるようなアルバムだ。こういった崇高な大作と呼ぶべき音楽作品の初期例のひとつであり、恐らく音楽史上最も偉大なアルバムのひとつが、ジョン・コルトレーンの『A Love Supreme(邦題:至上の愛)』である。
1959年、ジョン・コルトレーンはマイルス・デイヴィスの『Kind Of Blue』で演奏していた。インプロヴィゼーション(即興演奏)の基準点と目されるこのアルバムは、マイルス・デイヴィスの言葉を借りれば“モダン・ジャズをクールで超然とした本質にまで蒸留”している。真の卓越性というものに対するハードルがどれほど高いものなのか、彼は知っていたのだった。その5年後、自身のキャリアにおいて最も綿密に計画されたレコーディングで、ジョン・コルトレーンは自ら傑作を作り上げたのである。
ジョン・コルトレーンは当時、ロングアイランドの郊外で、2人目の妻でありハープ奏者兼ピアニストのアリスと共に子育てをしていた。この夫婦は精神哲学への興味を共有しており、ジョン・コルトレーンが新作の複雑な素案を携えて階段を降りてきた夏の日のことを、アリスは「山から降りてきたモーゼのようだった」と振り返っている。「予め全ての準備を整えられたのは、今回が初めてだよ」と妻に語ったジョン・コルトレーン。後にアルバム『A Love Supreme』となるこの組曲は4部構成で、それぞれに「Acknowledgement(邦題:至上の愛 パート1:承認)」「Resolution(邦題:至上の愛
『A Love Supreme』は元々、9人のミュージシャンから成るアンサンブル用にアレンジされていた。だがニュージャージーでレコーディング・セッションを行うことになった段階で(1964年12月9日に1日で完了)、ジョン・コルトレーンは彼のクラシック・カルテットと共にこのレコーディングに臨んだ。つまり、ピアノ担当にマッコイ・タイナー、ベース担当にジミー・ギャリソン、ドラムス担当にエルヴィン・ジョーンズ。そしてジョン・コルトレーン自身がテナー・サクソフォンを担当。また今回初めて、ジョン・コルトレーンがヴォーカルとしてもクレジットされている(第1部終盤のチャント部分を担当)。 「Acknowledgement」の別テイクでテナー・サクソフォンを演奏したアーチー・シェップは、「これはパワフルでスピリチュアルな作品だと思う。至高の存在(神)に対する、個人的な献身だね」と述べていた。
同作はジョン・コルトレーンのキャリアにおける絶頂期で、彼の人気を更に高め、グラミー賞の2部門にノミネートされたのに加え、1965年末の批評家投票でも軒並み1位に輝いた。その年の初めにマルコムXが暗殺されるという、一触即発の社会情勢の中で世に送り出されたこのアルバムは、魂の探求を訴える音楽的宣言とも呼ぶべきもので、天才的作品としてすぐさま称賛を受けた。ダウン・ビート誌のレヴューで5つ星を付けたドン・デマイケルは、その評の中で、同作が「聴き手の中に内省を促す」満ち足りた安らぎ放っていると解説。彼は『A Love Supreme』を‘芸術品’と呼んだ。
このアルバムの影響力は現代にまで広がっている。ジャズ・サックス奏者コートニー・パインは、『A Love Supreme』は彼が人生で最も繰り返し聴いたアルバムだと語り、またU2の曲「Angel Of Harlem」の中にも、このジョン・コルトレーンの傑作への言及がある。
Chasing Trane: The John Coltrane Documentary (Tuesday Film Series 5.9.2017)[layerslider id=”0“]ジャズ界から、より広い音楽の世界で決定的な足跡を残したのは、もちろんジョン・コルトレーンだけではない。カウント・ベイシーや、デューク・エリントン、ディジー・ガレスピーといった巨匠達の作品であれ、また感情を音楽という言語に翻訳する能力に長けたセロニアス・モンクであれ、同様のことが当てはまる。セロニアス・モンクと彼のスター・ミュージシャン仲間達(ソニー・ロリンズやマックス・ローチら)が、1960年のアルバム『Brilliant Corners』で成し遂げた自由奔放さも、同作が歴史的作品となっている理由だ。
アーティストが自身の音楽的な大計画を披露する“コンセプト”・アルバムという観点からすると、時系列がシンプルなおかげで、ジャズはポップやロック・ミュージックよりも先を行っていた。時にはそれが全く革新的な手法だったこともある。例えば1956年の画期的なアルバム『A New Sound, A New Star』で、ジミー・スミスがジャズ・オルガンのためのブルース+ビバップの青写真を作り上げた時がそうであった。また、スタン・ゲッツとブラジル人ギタリストのジョアン・ジルベルトが『Getz/Gilberto』でメロディとラテンを融合させるなど、新たな領域への挑戦を行ったミュージシャンもいる。
その他、芸術的オマージュを追求した者もおり、例えばスタン・トレイシーが1965年に発表した、想像力を掻き立てるアルバム『Under Milk Wood』には、詩人ディラン・トマスによる1950年代のラジオ・ドラマから着想を得た曲が集められていた。また、ホレス・シルヴァーの『Song For My Father』では個人的な探求が展開されており、極めて重要なその表題曲は、このミュージシャンがブラジル旅行をした時のことからインスピレーションを得ている。あるいは、マイルス・デイヴィスのグラミー賞受賞作『Sketches Of Spain』の影響もあるだろう。こういった芸術的な大胆さや、知性に訴える音楽の感覚は、ハービー・ハンコックのようなミュージシャンにより、今の時代にまで続いている。ハービー・ハンコックは現在70代だが、今も尚、ジャズ界の偉大なる実験者の一人であり続けている。
ロックやフォーク、カントリー・ミュージックの人気が高まるにつれ、そのジャンルにおける最も優れた実践家達の野心もまた、大きなものになっていった。60年代半ば、ボブ・ディランの『Bringing It All Back Home』が芸術的および商業的な成功を収めた後、ミュージシャン達はその影響を受け、時代を特徴づける音楽を作ろうと互いに競争し始めた。ブライアン・ウィルソンとビーチ・ボーイズが作り上げた交響曲『Pet Sounds』により、“ポップ”は壮大なアルバムの時代へと突入。 60年代後半になると、大胆で革新的かつ芸術的であると思われたがったロック・ミュージシャン達は、シングル市場が停滞期に差し掛かった時代でもあったため、LPレコードに一心に取り組むようになっていた。
The Beach Boys – Pet Sounds 50th – Mini Documentaryその分岐点となったのが1967年だ。ザ・ビートルズの『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』とジェファーソン・エアプレインの『Surrealistic Pillow』という衝撃的なアルバム直後から、アルバムというフォーマットがこれまでとは異なる挑戦的なサウンドを生み出すための空間と時間を与えてくれることに気づいた様々なバンドが、次々とその時流に便乗。レコード会社が3分間のシングルを絶え間なく生み出す生産ラインを求める時代は、消え去ろうとしていた。1968年には、アルバムの売り上げが初めてシングルのそれを上回るようになる。それを後押ししたのが、ハイファイ・ステレオ・サウンドの製造品質の向上と、全体でひとつの芸術作品となるアルバムという概念であった。LPアルバムの制作に費やされる期間は、数時間単位から数週間単位へ、場合によっては数ヶ月かかるようにもなった。
The Beatles – A Day In The Lifeまたこれは、ジャーナリズムがロック・ミュージックに対し、熟慮の上で注意を払うようになった時期とも重なっている。1966年2月、ポール・ウィリアムズという一人の学生が、ロックン・ロール音楽の評論に特化したCrawdaddy!という雑誌を立ち上げた。この発行人は、同誌が「ロックン・ロールを真剣に取り上げる史上初の雑誌」だと豪語していた。ローリング・ストーン誌が創刊されたのは、その翌年のことだ。
アルバムの台頭におけるもうひとつの重要なターニングポイントが、米連邦通信委員会が60年代半ばに下した指示である。同委員会は、共同所有のAM局とFM局は異なる番組を放送しなければならないと裁定。AM局よりも恐らく成熟したリスナーが対象となるであろうFM局が、突如としてロック・アルバムに門戸を開いたのである。ニューヨークのWOR-FMを含む幾つかかのラジオ局では、より長いアルバム収録曲をDJが抜粋してかけられるようになった。アメリカ全土のラジオ局が、すぐに同じことをするようになった。その後10年以内に、全米のFM局の聴取者数はAM局を追い越したのである。ロック・アルバムに基づくプレイリストを作成したAOR(アルバム指向のラジオ)が人気を高めたのも、この時期のことであった。
これはまた、シリアスなプログレッシヴ・ロック・ミュージシャン勢によるコンセプト・アルバムの登場にも好都合であった。プログレッシヴ・ロックのファンは主に男性で、その多くが自分達のことを、先駆者と熟練職人によって作られた新しいタイプの音楽の熱烈な愛好家であると感じていたのである。ロック・ミュージックが進化と向上を続けていた時代、プログレッシヴ・ロック・ミュージシャン達は、自分達こそが開拓者であると信じていた。エマーソン・レイク&パーマーのドラマー、カール・パーマーが、自分達は‘より質の高い音楽’を作っていると語っていた一方、イエスのジョン・アンダーソンは、時代の変遷により、ロックの進歩は‘より高次の芸術形式’へと踏み出したと考えていた。おそらくこれが、 “ポップ”が“ロック”に変わっていく究極の現れであった。
70年代の多くのアルバムの歌詞は、50年代および60年代のポップ・ソングよりも野心的だ。直喩や暗喩、寓話が続々と湧き出るようになり、エマーソン・レイク&パーマーはある曲で、大胆にも“兵器化されたアルマジロ(“アルマジロ戦車”)”の寓話を取り上げたほどである。おそらく『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』に触発されたであろうロック・バンド勢は、ビバップ時代における前衛作品の爆発的急増に匹敵するように思われた。アルバム制作においては、より統一したテーマを備えつつ、サウンドに関してはより異質の要素から成るべきだという信念があったのである。
ニューヨーカー誌2017年6月号でケレファ・サネは、この新ジャンルが永続的な人気を保っている理由をこう要約していた。「プログレッシヴ・ロックの開拓者達は、突飛な考えを信奉していた。奇妙な楽器や幻想的な歌詞、複雑な曲構成や難解なコンセプトのアルバム、派手なソロ、より派手なライヴ。観客は、メロトロンと呼ばれる新たな電子キーボードや、エイリアン司令官のようなコウモリの扮装をしたヴォーカリスト、ジョン・キーツの詩の引喩、そして人類の終焉を題材にした哲学的な寓話の全てを、ジェネシスの1曲(「Watcher Of The Skies」)で堪能できたのである」。
ジェネシスは、この道を切り開いたバンドのひとつであった。全長23分弱の驚異的な長尺曲「Supper’s Ready」について、ピーター・ガブリエルは「最後には聖書の黙示録の場面を歩いて行くことになる、個人的な旅なんだが…….このへんにしておこう」と要約している。
Genesis Watcher of the Skies Live Shepperton Studios 16mm HD – 30/31 October 1973ロック・バンドが壮大な雰囲気を生み出すもうひとつの方法として、オーケストラの活用があった。これはかつて、ジャズ・ミュージシャンが行っていた手法である。1943年、デューク・エリントンがカーネギー・ホールでの初コンサートのために作曲した「Jazz Symphony」は、彼にとって最も野心的な作品のひとつであった。オーケストラのサウンドは、1955年にヴァーヴから発表された画期的なアルバム『Charlie Parker With Strings』でも大きな効果を発揮していた。
ジャズとクラシックの融合における現代の代表的人物がチック・コリアで、彼はそれを1996年の『The Mozart Sessions』で結実させた。このアルバムは、ボビー・マクファーリンとセントポール室内管弦楽団と共に作った作品だ。マイルス・デイヴィスの元サイドマンだったチック・コリアは、高尚かつ野心的なアルバムを作りたいと常に考えていた。そして彼は2013年、コンコードから発表した『Trilogy』でそれを再び実現。この3枚組ライヴ・アルバムは、“目が眩みそうな音楽的自伝”と評されている。
チャーリー・パーカーの歩んだ道の跡に、ロック・ミュージシャン達が続いた。ロックとクラシック音楽とが一体となった世界は今では一般的だが、60年代においては画期的な手法であった。1967年の『Days Of Future Passed』でその道を拓いたのが、ムーディー・ブルースだ。この名作アルバムには、ピーター・ナイトが指揮するロンドン・フェスティバル・オーケストラが参加。その中心に据えられているのが、驚くほど素晴らしい「Nights In White Satin(邦題:サテンの夜)」である。ディープ・パープルの『Concerto For Group And Orchestra(邦題:ディープ・パープル・アンド・ロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラ)』もまた、もうひとつの決定的瞬間であった。同作ではジョン・ロードが立役者となり、このロック・バンドとロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団とのコラボレーションが実現している。
Deep Purple, London Symphony Orchestra – Smoke On The Water (Live)uDiscoverの「クラシック・オーケストラ・ロック曲25選」の中で、リチャード・ハーヴァーズは次のように語っている。「オーケストラを効果的に使用した他のプログレ実践者には、イエスがいる。彼らはリッチー・ハーヴェンスのカヴァー曲「No Opportunity Necessary, No Experience Needed」で、ジェローム・モロスが手掛けた映画『大いなる西部(原題:The Big Country)』のテーマ曲を引用。その後、リック・ウェイクマンが加入すると、イエスはオーケストラを必要としなくなった。彼のキーボード一式が、それと同じ仕事をしたからである。しかしながら、自身のソロ・アルバム『Journey To The Centre Of The Earth(邦題:地底探検)』で、リックはロンドン交響楽団を使用していた」。
他方において、時にはたったひとつの曲が大きな衝撃波を生み出すことがある。プロコル・ハルムの「A Whiter Shade Of Pale」や、ドアーズの「Light My Fire」がその好例だ。 1970年の終わり、ロンドンで3ヶ月以上に渡ってレコーディングされた『Led Zeppelin IV』には壮麗な曲が幾つか収録されているが、ジミー・ペイジとロバート・プラントが書いた荘厳な「Stairway To Heaven(邦題:天国への階段)」ほど名高い曲はほぼ存在しない。
また、哲学的テーマが創造的な衝動を刺激することもある。これまで数多くのミュージシャンが、オルフェウスとエウリュディケの物語を自分達の音楽に使用してきた。古代ギリシア神話は、個々の楽曲だけでなく、数え切れないほどの書物、演劇、詩、オペラ、バレエの他、多種多様なアルバムの着想の源となっている。そこに含まれるのが、ロシアの作曲家アレクサンドル・ズービンのロック・オペラや、元ジェネシスのギタリスト、スティーヴ・ハケットのインストゥルメンタル・アルバム『Metamorpheus』だ。おそらく最も興味深いのは、カントリー・ミュージシャンのアネ・ミッチェルの素晴らしくも風変わりなアルバム『Hadesdown』で、大恐慌後のニューオーリンズに、この神話を投影している。

文学に触発されて誕生した “純芸術”の名作アルバムもある。成功例を幾つか挙げると、まずはビリー・アイドルの『Cyberpunk』(ウィリアム・ギブスンの1984年の小説『ニューロマンサー(原題:Neuromancer)』から着想を得た)。また、ブルース・スプリングスティーンの『The Ghost Of Tom Joad』(ジョン・スタインベックの著名な『怒りの葡萄(原題:The Grapes Of Wrath)』)。そしてルー・リードの『The Raven』(エドガー・アラン・ポーからインスピレーションを得た数多くの作品のひとつで、その他には、アラン・パーソンズ・プロジェクトのデビュー・アルバム『Tales Of Mystery And Imagination(邦題:怪奇と幻想の物語~エドガー・アラン・ポーの世界)』等もそうである)。それからラッシュの『2112』(クレジットには “アイン・ランドの才能”への賛美が含まれている一方、アルバムの基本部分は彼女の中編小説『アンセム(原題:Anthem)』と並行。後には逆に『2112』全体が、グラフィック小説調のリリック・ビデオ化されている)。 そしてキャメルの『The Snow Goose』(ポール・ギャリコの同名短編小説が着想源)。更にピンク・フロイドの『Animals』(ジョージ・オーウェルの『動物農場(原題:Animal Farm)』からヒントを得た)。またデヴィッド・ボウイの『Diamond Dogs(邦題:ダイアモンドの犬)』も、ジョージ・オーウェルからインスピレーションを受けている。
Rush – Tears (Lyric Video)https://www.youtube.com/watch?v=pZNOPJsB7H4
もうひとつ、70年代の象徴的なアルバムは、英ケント州のいわゆるカンタベリー・シーンに属していたキャラヴァンの『In The Land Of Grey And Pink(邦題:グレイとピンクの地)』だ。トールキンの影響を受けたアートワークをジャケットに用いた本作は、このバンドの最高傑作だと見なされている。
壮大な音楽を作ろうという試みに人を駆り立てるのは、文学ばかりではない。歴史上の事件もまた、アルバムの構想の源となることがある。それは、例えばエリック・ブレイス&カール・ストラウブのフォーク・オペラ『Hangtown Dancehall』(カリフォルニアのゴールド・ラッシュの物語)のように、独立して存在するほとんど無名だが珠玉の作品から、アイアン・メイデンのような有数のバンドによる作品まで様々だ。彼らが2003年に発表した大作『Dance Of Death(邦題:死の舞踏)』には、力強い「Passchendaele」を含め、歴史的な背景における死を題材にした一連の曲が収録されている。
リック・ウェイクマンは、ウディ・ガスリーの1940年のアルバム『Dust Bowl Ballads』が全てのコンセプト・アルバムの父であり、ポピュラー音楽における数多くの後進に影響を与えてきた作品であると確信している人々の一人だ。カントリー・ミュージックにもまた、壮大なスケールの、そして社会的な主張をも盛り込んだアルバムが相応にある。1964年、ジョニー・キャッシュは『Bitter Tears: Ballads Of The American Indian』をレコーディング。荒涼とした音数の少ない収録曲は、アメリカ先住民に対する非人間的な蛮行を題材にした物語を中心に構築されている。当時、米連邦議会では、アフリカ系アメリカ人の生活向上を目指す公民権法が通過したばかりで、ジョニー・キャッシュは自身の歌が同様の人権問題に対して注意を喚起できたら、と考えていた。
“黒服の男”ことジョニー・キャッシュは、『America: A 200-Year Salute In Story And Song』と題するアルバムも制作。ここでは母国の歴史における暴力というテーマが全21曲に渡って貫かれており、ビッグフット酋長の伝説から、エイブラハム・リンカーンのゲティスバーグ演説、そしてアラモの虐殺に至るまで、あらゆる題材をジョニー・キャッシュは扱っている。
しかしながら、カントリー・アルバムは深刻な社会的テーマ抜きでも、芸術的な大志を持つことが可能だ。 エミルー・ハリスは1985年のアルバム『The Ballad Of Sally Rose』を、自ら“カントリー・オペラ”と呼んでいた。同作のテーマは、野性的で酒好きのミュージシャンを恋人兼助言者(漠然とグラム・パーソンをモデルにしている)に持つ、一人の歌手の人生だ。ドリー・パートンとリンダ・ロンシュタットの参加も仰いでいる収録曲は、それぞれが流れるように繋がり合っており、ほとんど連続しているような勢いを感じさせる。偶然にも、ジョニー・キャッシュとエミルー・ハリスの両者は、西部開拓時代の無法者ジェシー・ジェイムズを主人公にした壮大な物語が描かれているコンセプト・アルバム(『The Legend Of Jesse James』)に、ザ・バンドのリヴォン・ヘルム共々参加している。
その他、カントリーの大作には、ウィリー・ネルソンの『Red Headed Strange』や、ケニー・ロジャース&ザ・ファースト・エディションが1968年に発表した2枚組アルバム『Ballad Of Calico』がある。カリフォルニアの町キャリコを舞台にした曲で全体が成っている後者では、バンドの各メンバーがヴォーカルを担当し、“極悪非道のビル”や“郵便配達犬ドーシー”といった、異なる登場人物達を演じている。また、厳密にはカントリー・ミュージックではないが、繰り返し登場するテーマである米国文化の享楽主義的な放蕩ぶりと浅薄さを扱った、イーグルスの「Hotel California」も言及に値するだろう。
政治的な関心は、重要かつ高尚なアルバムや曲を生み出す上で、これまで大きな役割を果たしてきた。そこにはグリーン・デイから、ニーナ・シモン、カニエ・ウェストまで、多彩なミュージシャン達による壮大な音楽が含まれている。ジョーン・バエズは、アウグスト・ピノチェト大統領の独裁政権下で苦しんでいるチリ国民のため、スペイン語のアルバム『Gracias A La Vida』をリリースした。ギル・スコット=ヘロンは当初、作家としてデビュー。1970年の詩集『Small Talk At 125th And Lenox』は後に、元小説家の彼自身がパーカッションに乗せて歌を付け朗読する形の曲となった。シカゴ生まれのこの活動家は、70年代、『Pieces Of A Man』や『Winter In America』を始めとする重要なアルバムの数々を発表。自身の言葉を借りれば、それによって彼は“米国における黒人の経験を全方位から”描くことができるようになった。
想像力を刺激する別の方法としては、“もう一人の自分”の活用があった。最も有名なのが『Sgt. Pepper’s…』のペパー軍曹だが、デヴィッド・ボウイの『The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars(邦題:ジギー・スターダスト)』もまた、素晴らしく印象的である。ピンク・フロイドの『The Piper At The Gates Of Dawn(邦題:夜明けの口笛吹き)』は歴史的傑作のリストには必ず入るアルバムだが、2枚組アルバム『The Wall』は、更にその上を行っていた。社会的に疎外されている主人公ピンクの物語を描いた同作は、史上最も偉大なコンセプト・アルバムのひとつだと見なされている。
それと同じカテゴリーに入るのが、ザ・フーの『Tommy』だろう。これは、ピート・タウンゼントが、40年以上一言も発せずにいたインド人導師メヘル・バーバーの教えに傾倒していた時に作られたアルバムだ。ピート・タウンゼントはこの “ロック・オペラ”を、”聴覚、発話、視覚に障害を負った少年”を主人公とする精神的な寓話的作品だと考えていた。本作のリリース(1969年5月)は、重要な文化的事件と捉えられている。
The Who – Pinball Wizard (Live)時として、ミュージシャンが自身の”アート”をあまり真剣に受け止めていないふりをすることもある。ジェスロ・タルの『Thick As A Brick(邦題:ジェラルドの汚れなき世界)』にはたった1曲のみしか収録されておらず、それを2部に分けて半分ずつアナログ盤LPの表裏に収録。これは皮肉を込めた反コンセプト・アルバムとして書かれた作品だった。だが不思議なことに、このパロディ作は結局、コンセプト・アルバムの名作のひとつに数えられるようになってしまっている。それと同じくらい風変わりなのが、スモール・フェイセスの『Ogdes’ Nut Gone Flake』だ。そのアルバムB面では、(コメディアン俳優の)スタンリー・アンウィンがスパイク・ミリガン風に訳の分からない話を語るという形で、「Happiness Stan」の奇妙な物語が展開されている。
最高傑作に位置づけられるアルバムの中には、ある心理的状態や情緒を生み出すものもある。例えばザ・キンクスの『The Kinks Are The Village Green Preservation Society』が掻き立てる、切なる郷愁感がそうだ。以前は、短く鋭い風刺的な曲を数多く作っていたザ・キンクスだったが、やがてひとつの主題を中心にして統一された意欲的な大作の制作へと向かうようになり、この『The Kinks Are The Village Green~』の次には、より長い物語を描いた『Arthur (Or The Decline And Fall Of The British Empire)(邦題:アーサー、もしくは大英帝国の衰退ならびに滅亡)』を制作。不満を抱えた若い労働者を題材に、社会的な主張と鋭い見解を示したこのアルバムは、幅広い称賛を受けた。
成功を収めた主要作品を持つミュージシャンの場合、マイナーな傑作が見逃されることがある。フランク・シナトラが1970年にリリースした『Watertown』がその好例だ。この偉大な歌手が11曲に渡って歌い上げているのは、妻に捨てられた男の感傷的な物語で、過小評価されているが実に素晴らしいアルバムに仕上がっている。
ミュージシャンの中には、生まれながらにして、複雑かつ挑戦的な音楽以外はほとんど作れないように思える者もいる。ベックや、パティ・スミス、フェアポート・コンヴェンションの1969年の大作『Liege And Leaf』でギタリストを務めてもいたリチャード・トンプソン、ジャクソン・ブラウン、グレッチェン・ピーターズ、エルトン・ジョン、ティム・ハーディン、そして『American Gothic』のデヴィッド・アックルズや、 1989年の『Car Wheels On A Gravel Road』でブレイクしたルシンダ・ウィリアムズらは皆、このカテゴリーに当てはまる。同じことが、グレイトフル・デッドやジェファーソン・エアプレインの代表作におけるサイケデリックなヴィジョンにも言えるだろう。
Beck Song Reader – Heaven’s Ladder ft. Beck (Lyric Video)もちろんその気になれば、このリストは無限に続けることが可能だ。だが、ここでヴァン・モリソンの『Astral Weeks』に触れずにいるとしたら、怠慢極まりないことだろう。チャーリー・パーカーのドラマーを務めていたコニー・ケイが参加しているこのアルバムは、時代を超越したジャズ・ロックの傑作だ。『Astral Weeks』の発表以前、ヴァン・モリソンは「Brown Eyed Girl」等のシングルで主に知られていたが、このアルバムはひとつの独立した作品として意識的に作られており、アルバムの各面には「In The Beginning」(=初め)と「Afterward」(=その後)というレーベルが付けられていた。同作は現在も、音楽と想像力によって打ち立てられた偉業であり続けている。
芸術的野心の高みを一貫して目指してきたもう一人のミュージシャンが、トム・ウェイツだ。トム・ ウェイツは40年以上に渡り、一連の壮大なアルバムの中で、酒やドラッグなど自堕落な夜を過ごす登場人物を通じ、アメリカの下層社会の生活を追求し続けてきた。1987年の『Franks Wild Years』は、フランク・オブライエンという名の落ちぶれた男が主人公で、『Un Operachi Romantico In Two Acts』という副題が付けられていた。
その後に続く音楽の流れに影響を及ぼすようになるバンドもいる。タンジェリン・ドリームは、印象主義的なエレクトロニック狂想劇と言えるアルバムの数々を制作。リーダーのエドガー・フローゼは、ハンガリーの前衛作曲家リゲティ・ジェルジュ・シャーンドルからインスピレーションを得ており、『Atem』のようなアルバムを作る際には「他の人々や自分自身の能力の範囲に対し、勇気を持って尊敬の念を示すため、小さな指標を残す」ことを試みていると語っていた。その指標を目指す者達が後に続き、多くのニュー・エイジ・バンドを触発したという点において、タンジェリン・ドリームは影響を発揮した。
壮大な音楽の制作に向けた探究心は、21世紀にも赤々と燃え盛っている。眠りの神経科学を題材にした、マックス・リヒターの画期的なコンセプト・アルバム『SLEEP』は、8時間24分21秒という長さの作品だ。 2017年5月、ロンドンのバービカン公演で同作が披露された際には、観客にベッドを用意した“外泊演奏会”として実施された。
Max Richter – Dream 3 (in the midst of my life)充実した内容の音楽を創っている現代的なバンドには、他にスコットランドのモグワイがいる。エイフェックス・ツイン(リチャード・デヴィッド・ジェイムスの別名のひとつ)によるエレクトロニック・ミュージックもそこに含まれるだろう。またテキサスのロック・バンド、エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイは、自身の印象的なアルバム群を“精神浄化作用のあるのミニ交響曲”と呼んでいた。
野心的なコンセプト・アルバムを目下制作しているミュージシャンのリストに加えるのに相応しい人物に、グラミー賞にもノミネートされたプログレッシヴ・サイケデリック・バンド、ポーキュパイン・ツリーの創始者であり、ギタリスト兼フロントマンだったスティーヴン・ウィルソンがいる。2017年にリリースされる待望のアルバム『To The Bone』(Caroline International Records)について、スティーヴン・ウィルソン自身が語るところによれば「『To The Bone』は、多くの点において、僕が若い頃に愛してやまなかった非常に野心的なプログレッシヴ・ポップ作品からインスピレーションを得ているんだ。例えば、ピーター・ガブリエルの『So』や、ケイト・ブッシュの『Hounds Of Love』、トーク・トークの『The Colour Of Spring』、そしてティアーズ・フォー・フィアーズの『Seeds Of Love』等だね」。
同アルバムが扱っている題材の領域について、スティーヴン・ウィルソンは次のように語っている。「歌詞的には、今作の11曲は、真実というものはどうやら自由に曲げることが可能な概念であるように思える今の時代の被害妄想的な混沌から、難民やテロリストや宗教的原理主義者達の日常生活についての見解、そして僕がこれまでのキャリアで作った曲の中でも最も喜んで受け入れている素朴な現実逃避主義まで、多岐に渡っている。一家全員がそれぞれ楽しめるものが揃っているんだ」。
Steven Wilson – Pariah ft. Ninet TayebSteven Wilson – Song Of I ft. Sophie Hunger偉大なアルバムを生み出すための刺激となるものが、喜びに満ちた現実逃避であれ、政治的な怒りであれ、詩的な叙情性であれ、個人的な精神的探求の旅であれ、それは一番重要なことではない。 大事なのは、ジョン・コルトレーンが言ったように、“聴き手の魂に語りかける”ことなのだ。そうすれば“壮大な音楽”の歴史の一頁に、あなた自身が寄与する可能性が高まるだろう。
Written By Martin Chilton
[関連記事]